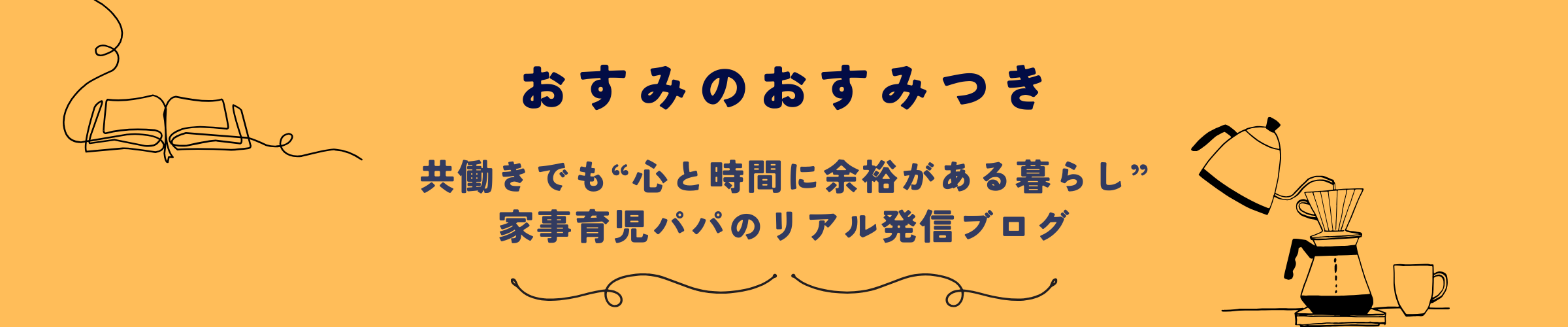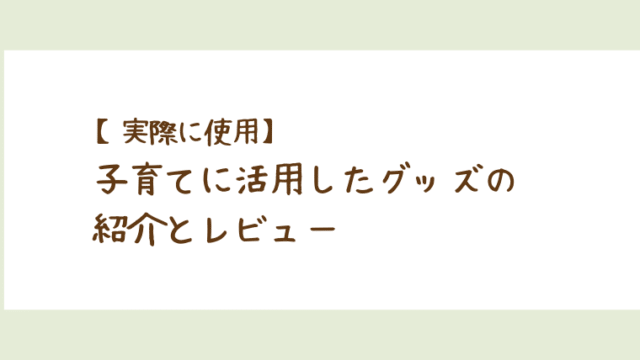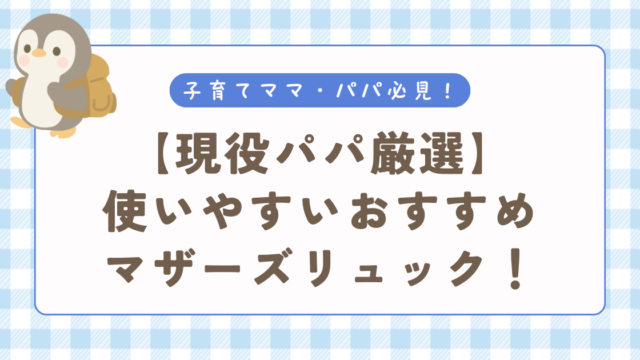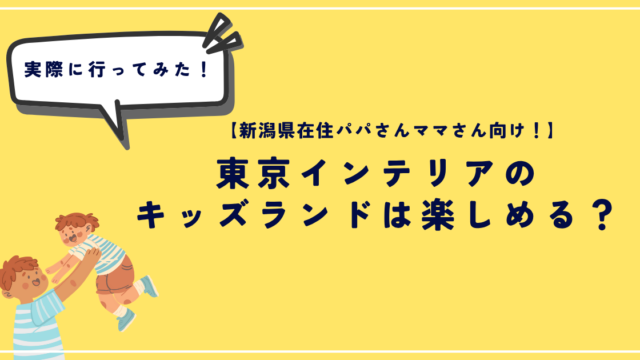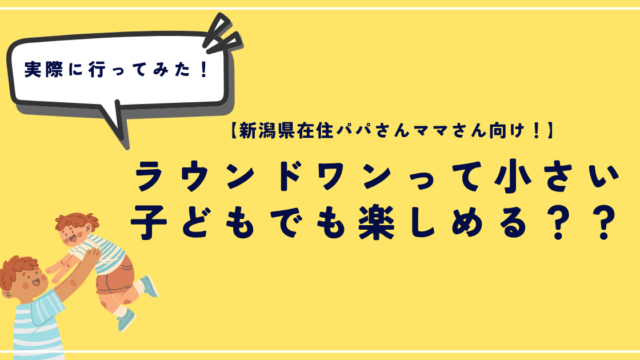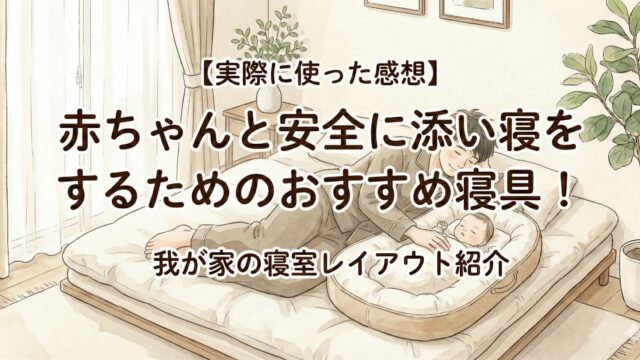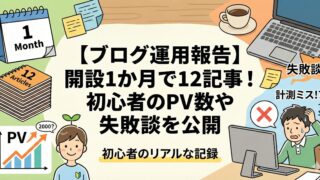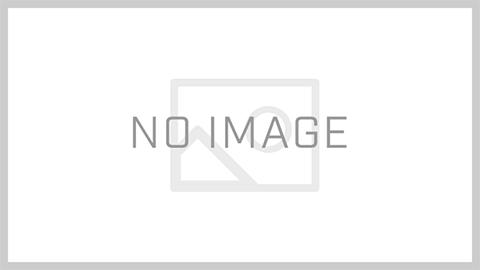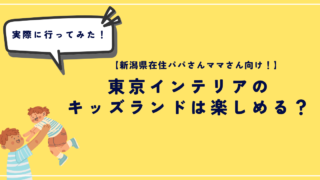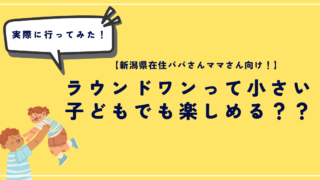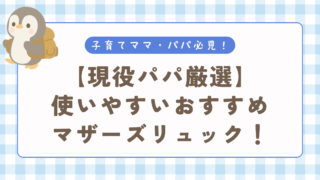子供の偏食対策!食べてくれないときの対応と考え方

こんにちは!おすみです!
今日は子供の偏食について書いていこうと思います!
うちの子も3歳になり、食べられるものもどんどん増え、バリエーション豊富な料理が食卓に並ぶようになりました。毎日料理をしている自分もより気合を入れて作るようになったのですが、
好きな物しか食べてくれない・・・。
色々作ったのに決まった物しか食べない・・・。
こういう経験されている方、多いのではないかと思います。
僕も毎日料理をしていて、子供の栄養を考え色々と作るのですが、気合を入れたときに限って食べてくれないんですよね。
食べてくれない日が続くと、子供の栄養不足が気になって親として焦りを感じたりイライラしてしまいます。
今日は偏食とはなんなのか、そしてどのように向き合っていくべきなのか対応策を考えていこうかと思います!!
そもそも偏食とは?
偏食の定義
偏食:食品の好き嫌いが極端であり、ある特定の食品しか食べられないことにより食事が偏ること
以上のように定義されています。
- 味覚の発達段階により、苦みや酸味に過敏に反応することがある。
- 感覚の過敏さなど、身体的・発達的な要素が影響する子もいる。
- 自我が芽生える時期に「食べたくない」という意思表示として現れる場合もある。
発達や感覚の問題、味覚の成長段階、心理的要因などが複雑に絡んで起こる自然な現象で、多くの子どもに見られる現象ということです。
偏食による体への影響
偏食により食べるものが偏ると、当然栄養が偏り、心身共に様々な症状が出やすくなります。
体の症状
- 疲れやすい、元気がない:エネルギー不足やビタミンB群不足が原因で、体がだるく感じたり、集中力が低下したりします。
- 風邪をひきやすい:免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。
- 貧血:鉄分不足などで、立ちくらみ、めまい、息切れなどが起こることがあります。
- 肌荒れ、口内炎:ビタミンAやB群の不足が原因で、肌の調子が悪くなったり、口内炎ができやすくなったりします。
- 成長の遅れ:栄養不足が続くと、身長が伸び悩むなどの成長障害につながることがあります。
精神・行動面の症状
- 集中力の低下、ぼーっとする:脳のエネルギー不足や、集中に必要な栄養素の不足が影響します。
- イライラ、不機嫌、癇癪:感情のコントロールに必要なビタミンB群などが不足すると、感情の起伏が激しくなることがあります。
- 気分のムラ、不安感:些細なことでくよくよしたり、漠然とした不安を訴えたりすることがあります。
- 不眠:寝付きが悪かったり、悪夢を見たりすることがあります
食べ物のどんな特徴が感じられるか
私たちが口にするものはすべていろんな特徴を持っています。
- 見た目:色合い、盛り付けの綺麗さ、形といった食べ物の姿形
- におい:甘い匂い、酸っぱい匂い、生臭いにおいといった食物由来のにおい
- 形状:固体、液体、どろどろしているといった形状の違い
- 味:甘い、辛い、酸っぱい、苦いといった味覚への刺激
- 食感:ツルツル、ザラザラ、パリパリ、ガリガリといった口腔内の感覚
以上のように、食事をする際には、まず”視覚”で食べ物の姿形を認識し、”嗅覚”でにおいを感じとる。そして”触覚”(口腔内感覚)で食べ物の特徴を感じながら”味覚”で味を感じる。といったプロセスが発生します。人間の五感のうち四つも使用しているわけです。
うちの子の特徴は、
- ご飯は白米のみ! ふりかけやチャーハンなど色つきのご飯はNG
- 白い食べ物が好き 牛乳、豆腐といった色が白いものが大好き
- 甘いものが最優先 ご飯よりもお菓子を優先
(甘いものを覚えさせてしまった自分の責任です、、、泣)
偏食が起きるメカニズム
子供が偏食を起こすメカニズムとして以下の要因が挙げられます。
- 生理的要因
子どもは大人よりも味覚が敏感で、特に苦味・酸味を「危険な味」と認識しやすい傾向があります。これは人間の進化的な防衛反応で、苦味=毒、酸味=腐敗と感じて避ける仕組みが本能的に備わっているためです。また、嗅覚や視覚からの情報も強く影響し、見た目や匂いで拒否反応を起こすこともあります - 発達的要因
食べる動作には、舌や顎、唇などの協調運動が不可欠です。口腔機能が未発達な段階では、噛んだり飲み込んだりすることが難しく、柔らかい食べ物や特定の食感に偏る傾向が見られます。発達が進むことで徐々に多様な食品を受け入れられるようになります。 - 心理的要因
自我の芽生える2~3歳頃には、「イヤイヤ期」による心理的要因での偏食も増えます。これは食べ物を拒否することで自己主張を表す行動であり、発達上自然なプロセスです。また、未知の食材への警戒心(ネオフォビア)も関係し、経験を重ねて「安全だ」と理解することで克服されていきます。
以上のように、子供の成長過程のなかで、食べ物を食べ物として認識がうまくいってなかったり、味覚の未発達によって拒否反応が出てしまっているようです。
人間が食べ物を食べ物として認識できたり、好みが現れるのは、要は何度も食べることによって脳が記憶するわけですね。なので食べる経験がまだまだ浅い子供にとって、偏食が出るのは至極真っ当なことといえます。
例えば、大人の我々でも、まったく知らない国の見たこともない料理を出されたら、食べるのをためらってしまいますよね。子供の偏食はまさにそのような状況なのではないかと思います。
偏食に対してできる親の対応
声掛けを変えてみよう
子どもの偏食に対して親ができる対応策は、「無理強いせず、楽しく・少しずつ」を基本に、環境・心理・経験の3つの側面からアプローチすることが効果的です。
- 「一口だけ食べてみよう」とチャレンジを促してみる
- 「見てみよう」「においはどうかな」と口に入れる準備をさせてみる
- 一口でも食べたら「すごいね!」とオーバーに褒める
- 好きなキャラクターやぬいぐるみなどを活用して声をかける
例:くまのぬいぐるみを使って、人形ごっこのように食べるのを促してみる
- 食べないことを叱る 例:「なんでたべないの!」
- 脅すように食べさせる 例:「食べないと鬼がくるよ!」
- 無理やり口に入れる
まずは声掛けから取り組んでみましょう。悪い例のように対応すると、子供に食事は
怖いもの、嫌な物とネガティブなイメージがついてしまう可能性があります。
楽しい環境を整えよう
少しでも食べてもらうには、楽しい食事環境を整えるのも効果的です。
- 家族みんなで楽しく食事を囲む「共食」を心がける
- プレッシャーを与えず、楽しいムードを演出するためにキャラクター食器やピクニック形式を取り入れる。
- 食事時間は短めに設定し、長時間食事に拘束しない
- さっさと食べるよう急かさない
以上のように、子供が楽しめる食事環境を整えることも効果的です。
うちの子は、ディズニーの食器やコップなど、本人のお気に入りの食器を使うことで比較的食べてくれるようになりました。また、食器のどこに盛り付けるかもこだわりがあるようなので、本人に「どこに」「なにを」「何個置くか」と本人の意思を確認しながら盛り付けることで、以前よりも食べるようになりました。
食の工夫と体験をさせてみよう
食形態を工夫してみたり、一緒に調理をすることで改善がみられるかもしれません。
- 苦手食材は、調理法を変える
(例:焦げ味を減らす、加熱で酸味を飛ばす、細かく刻むなど) - 好きな料理や味付けに混ぜることで「苦手食材への橋渡し」ができる
- 親子で買い物や料理を一緒にすることで、子どもが「自分が選んだ」「自分が作った」という気持ちを持つようになり、食への興味が高まる。
以上のような対応策もあります。
苦手食材を見えないように調理して食べさせるやり方もありますが、根本的な解決になっていないように感じるので僕は実践していません。
それよりも、ちゃんと見てその食材とわかる形で出して、例えば好きな物と一緒に食べさせてみたり、「今日は一口だけ」と少しずつ慣れてもらうように促しています。
いっそのこと遊びながら食べよう
先に述べた内容を実践しても改善が見られない場合があると思います。
そこで僕が良く実践している食べ方が、”いっそのこと遊びながら食べる”です。
このような食べ方をすると多分こう思われます。
行儀が悪い!
教育によくない!
というように批判されること間違いなしです。
ですがそもそもの話、偏食で焦る親の心理としては、”食べないことでの栄養不足”が一番だと思います。だったらどういう形であれ、口にしてくれるのであれば遊びながら食べても
いいじゃないかと僕は思います!
うちで取り入れてる食べ方としては、
- 好きなアーティストのダンス動画を見て踊りながら合間に食べる
- おままごとをしながら食べる
- 家を走り回って休憩時に食べる
といったように、けっこう本人の好きにさせた上で食べさせています。
もちろん、「遊ぶなら今日はここまで食べるんだよ。」と簡単なルールを設けることで、本人も承諾してくれますし、きちんと食べてくれます。(どうしても機嫌が悪くダメな時もあります・・・)
偏食に対する親の心持ち
成長過程だから”仕方ない”と割り切る
先に述べたように、子供はまだまだ成長中で、様々な経験を通すことで感覚が育ちます。
視覚、嗅覚、触覚、味覚、(一緒に調理を行えば聴覚も使うことになりますね)
この五感を育てている最中なので、大人よりも好みが分かれるの仕方のないことなのです。
色々な食材を試し、少なからず食べてくれるものはあるはずです。
焦らずに少しずつ試していきましょう。
1日1食でも食べてくれれば御の字精神
人間には「1日3食食べる」といった固定概念が染みついています。
そのため朝・昼・晩ときっちり食べさせないといけない!と考えがちです。
これに関して、1食でも食べてくれれば御の字精神で対応してよいと思っています。
長期間1食生活が続けば確かに栄養の偏りは出てくると思いますが、短期間であればそこまで影響はないように思います。
人間はどうしても過剰にネガティブに考えがちですが、1食、2食抜いた程度で、死んだりしません。気楽に対応していきましょう。
うちの子はひどいときは朝はヨーグルトだけ、夜は小さい豆腐1個だけといった時もありました。それでも身長100cm、体重15kgと3歳の女の子の平均よりも少し上くらいまですくすく育っています。
どうしてもだめな時はお菓子や捕食に頼ろう
どんなに対策してもダメな時は、お菓子や捕食に頼ってもよいと思っています。
昔に比べて栄養補助食品や栄養がプラスされたお菓子がたくさん販売されています。
そういったものに頼るのもありだと思いますし、そうでもしないと親側のストレスが蓄積してして心身に影響が出てしまうため、頼れるものはどんどん活用していきましょう。
食事量が少ないと感じたときは、おやつにカルシウム入りのウエハースを上げたり、野菜ジュースをおやつに出したりもしています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
- 偏食は子供の成長過程であり、偏食になるのは仕方のないこと
- 様々な対応を通して、自分の子供に適した食べさせ方を見つけよう
- イライラする気持ちもわかる。けれども頼れるものに頼りながら乗り切ろう
- よそはよそ、うちはうち!人に何と言われようと子供が食べてくれるなら遊びながらだっていい!
ここまで見てくれた方の大半は子供の偏食で悩んでいる親御さんかと思われます。
現に自分も悩んでたくさん調べて色々と試した経験があります。
それでも食べなくてイライラすることもありますが、最近は”まぁ育ってるし大丈夫でしょ”と気楽に考えて対応しています。
今日の記事が少しでも同じ悩みを持つ方の助けになれば幸いです。
ありがとうございました!